アンブシュア(口の形)や指使いも大切ですが、実は“息の使い方”も音を変える大きなポイントなんです。
今回は、「効果的な息の使い方」、そして「響く音を作るための呼吸法と練習法」を紹介します。
目次
STEP:1 息の“量”ではなく、“スピード”が大事!
「よく響くを出すには、たくさん息を入れればいい」と思いがちですが、実はそうではありません。
たくさん息を入れたらたしかに大きい音はなるかもしれませんが、それは「大きいだけの音」になってしまう可能性が高いです。
大きいだけの音で吹いても、メロディの繊細さを表現することは難しいですし、聴いている人も心地よく聞くことは出来ないでしょう。
サックスの音を決めるのは息の“量”ではなく“スピード”と“太さ”です。
太い筒にゆっくり息を吹くより、細いストローに「スーッ」と速い息を通すほうが勢いがありますよね。
サックスも同じで、まとまったスピードのある息は、リードををしっかり振動させ、音にハリとツヤを与えます。
STEP:2 速いだけでなく、適切な息のスピードを覚えよう
息のスピードは「速ければいい」というわけではありません。
楽器には“その楽器が一番よく響く息の速さと量”があります。
強すぎる息は音を荒くし、弱すぎる息はこもったり、覇気のない音になってしまいます。
大切なのは、「息の速さを感じながら、楽器が一番響くポイントを探して保つこと」です。
また、曲によっても適した息の使い方は異なります。アップテンポな曲や勢いのある曲は速い息を使う方が良い場合が多く、ゆったりとしていて歌い込むような曲は比較的ゆっくりとした、暖かい息をイメージして吹き込むと良いでしょう。
STEP:3 響く音は「よくまとまって速い、でも無理のない息」から生まれる
プロのサックス奏者の音が豊かに響くのは、常に息の流れが整っているからです。
息のスピードが一定で、無理なくリードを振動させることができると、自然と響きが生まれます。
一方で、力を入れすぎたり、息の速さがバラつくと、音がつぶれたり不安定になります。
「頑張って吹く」よりも、「気持ちよく流れる風を保つ」ことを意識してみましょう。
STEP:4 ロングトーンで「息の速さを保つ」練習
息のスピードを感じ取るために、もっとも効果的なのがロングトーンです。
1つの音を長く伸ばすとき、音量を変えても“息の速さ”は落とさないように意識しましょう。
特に弱く吹く「p(ピアノ)」のときこそ、息のスピードを落としすぎないよう注意する必要があります。
pのような弱奏で息のスピードまで落ちてしまうと、ハリのない音になってしまいます。よく通るpにするためにはこの点を意識すると良いでしょう。
また、ロングトーンの最中に安定した音で吹くためにはお腹の支えも重要なってきます。重心を下のほうに置くイメージで、「息の線が途切れていないか」「音の響きが変わっていないか」を耳で感じながら練習すると、自然と息のコントロール力がついていきます。
STEP:5 胸式呼吸ではなく「腹式呼吸」で支える
息のスピードを安定させるためには、呼吸の仕方もとても大切です。
サックスでは、胸で吸う「胸式呼吸」よりも、お腹で吸う「腹式呼吸」が基本になります。
胸式呼吸は肩や首に力が入りやすく、息が浅くなってしまいます。
一方で腹式呼吸は、お腹や背中の筋肉を使って深く息を吸えるため、息の流れが長く・安定します。
吸うときは肩を上げずに、お腹をふくらませるように吸い、吐くときはお腹を軽く引き締めて、一定のスピードで息を送り出しましょう。
ロングトーンの項目でも登場した、この「お腹で支える」感覚がつかめると、音の響きがぐっと豊かになります。
STEP:6 まとめ 〜“速さ”よりも“響く息”を探そう〜
音を良くするために、息の使い方はかなりの重要ポイントです。
息のスピードや太さ、お腹の支えを使って一定のブレスで吹くことが大切になってきます。
最終的に目指すのは、楽器がいちばん美しく響く息の量と速さを保てるようになることです。
そのために、腹式呼吸で安定したブレスを身につけ、息の流れをコントロールしていきましょう。
毎日のロングトーンで、少しずつ“響く息”の感覚をつかんでいけば、もっと自由に、美しい音を奏でられるようになるはずです♪
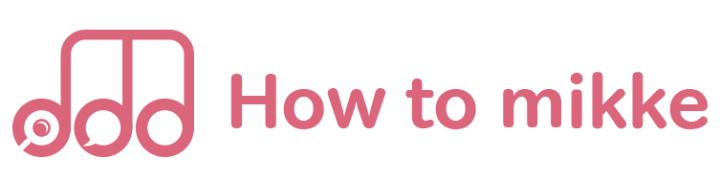


コメント0件