目次
STEP:1 サックスを始めるときに迷う「アルト」と「テナー」
サックスにはソプラノ、アルト、テナー、バリトンの4種類があります。違いは主に大きさと音域です。
部活では担当楽器が割り振られることも多いですが、自分で始めるならまず候補にあがりやすいのはアルトかテナー。扱いやすさや人気の点から見ても、この2本は初心者にとって現実的な選択肢といえます。
STEP:2 アルトとテナーの基本的な違い(サイズ・音域・吹奏感)
アルトとテナーは見た目はよく似ていますが、役割や音色にははっきりとした違いがあります。
アルトは小ぶりで音域が高め。クラリネットやトランペットのように主旋律を担当することが多く、明るく華やかな音色が特徴です。
一方テナーは中低音を受け持ち、落ち着いた厚みのある音が魅力。吹奏楽ではホルンやユーフォニウムのように副旋律やハーモニーを担い、全体を下から支える役割を果たします。
STEP:3 演奏シーンでの違い:吹奏楽/ジャズ/ポップス
演奏シーンによっても、アルトとテナーの立ち位置は変わります。
吹奏楽ではアルトがソロや主旋律を担当し、華やかさを引き出す一方で、テナーは副旋律やハーモニーを受け持ち、厚みを加える存在です。
ジャズやビッグバンドではどちらもソロ楽器として活躍します。たとえば《イン・ザ・ムード》や《茶色の小瓶》といった定番曲では、アルトの軽快さとテナーの深みが曲の雰囲気を大きく左右します。
ポップスでもサックスは印象的に使われることが多く、《Just the Way You Are》のように耳に残るフレーズで彩ることがあります。
STEP:4 中学でテナーサックスを担当することに。大きめの楽器に慣れるまで
私が初めてテナーを吹いたのは中学の吹奏楽部でした。最初に思ったのは「長っ!」。アルトに比べて大きく重いため、親指に負担がかかりやすく、痛みを感じることもしばしばありました。初心者に多い悩みだと思います。
最初の数か月は「音は出るけれど響かない」「音程が安定しない」ことの繰り返し。それでも続けるうちに気づいたのは、親指だけで支えようとせず、ストラップに重さを預けること。そして、力むのではなくリラックスして息を入れること。この2つを意識することで、音が少しずつ安定してきました。
STEP:5 高校でバリトンに出会い、低音に惹かれた3年間
高校では人数の関係でバリトンを担当することになりました。テナーよりさらに大きく、最初は息が全然続かず「こんなに違うの!?」と驚いたのを覚えています。
そこで役立ったのが、壁にティッシュを軽く当て、そこに息を一定に当て続ける練習。荒く切れた息ではティッシュが揺れてしまい、まとまりのある音にはなりません。呼吸を一点に集中させる意識が、安定した響きを作る基礎になりました。
さらに、音を出すときはお腹から息を頭の上までまっすぐ通すイメージで響かせるように指導を受けました。その結果、べちゃっと広がる音ではなく、クラシックに向いたまとまりのある響きに近づいた感覚があります。実際、奏者の中にも「クラシックでは透明感やまとまりを重視する」「低音域を豊かに響かせたい」と語る人は多く(ヤマハ公式や演奏家のインタビューなど)、自分の感覚もそれに近かったのだと思います。
低音パートは「音量」よりも安定感が大切。音を途切れさせず、まっすぐ息を送り続けることを意識したことで、アンサンブル全体の響きがまとまりやすくなることを学びました。
STEP:6 大学ではテナーを購入、時々バリトンも演奏
大学に進学すると、自分の楽器を持つ必要がありました。本当はバリトンを続けたかったのですが、価格も維持費も高く、現実的に選んだのはテナーです。
購入の際は楽器店で何本も試奏し、メーカーごとに音色や吹き心地がまったく違うことに驚きました。そこで学んだのは、サックスはカタログや値段だけで選ぶのではなく、必ず自分で吹いて確かめることが大切だということ。費用ももちろん大事ですが、納得できる一本を選ぶことが、長く続けるコツだと思います。
STEP:7 どちらを選ぶ?体格・好み・費用で変わるサックス選び
アルトとテナーのどちらにするかは、体格や予算といった現実的な条件に左右されます。アルトは軽くて扱いやすく、価格も手頃なモデルが多いので最初の一本に選ばれやすいです。一方、テナーは本体が大きく価格もやや高めですが、中低音の厚みは唯一無二の魅力です。
サックスは長く付き合う楽器です。費用面は大切ですが、「せっかく買うなら心から納得できる一本」を選ぶことが、後悔しないためのポイントだと思います。
STEP:8 まとめ:私にとっての「低音の魅力」とテナーの現実性
アルトとテナーは見た目は似ていますが、音域や役割はまったく異なります。アルトは華やかさと目立つ存在感、テナーは厚みのある響きで全体を支える頼もしさ。
私自身、高校でバリトンに夢中になって以来、低音の響きに強く惹かれてきました。大学では現実的にテナーを選びましたが、今も低音がもたらす心地よさに支えられています。
最終的に大切なのは「自分がどんな音を出したいか」。その気持ちを軸にすれば、きっと自分に合った一本に出会えるはずです。
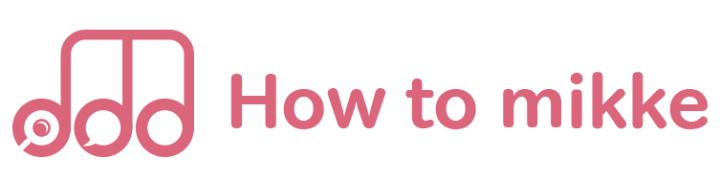


コメント0件