目次
STEP:1 ギターの指板上で全全半全全全半を身につけよう。
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの音の間隔はどうなっているでしょうか?ギターを弾くにはそのことはとても大切のことになります。なぜかというとギターのフレットはすべて半音ずつに区切られているからです。この半音間隔を使って自由に音を出す楽器がギターであるといえますね。では音階の各音の間隔はどうなっているのでしょうか。
それは全・全・半・全・全・全・半となっていますね。ドとレの間隔は全音。レとミの間隔は全音。ミとファの間隔は半音。ファとソは全音。ソとラは全音。ラとシは全音。そしてシとドは半音となっています。ファとドの前だけが半音で他はすべて全音ですので、まずは全・全・半・全・全・全・半を覚えましょう。それがギターを弾く第一歩であり、それを知っていればまずはギターでドレミの音階を弾くことができます。
STEP:2 開放弦からフレットへと順に半音ずつ高くなる
ギターのフレットを見てみましょう。金属のバーが横に何本も並んでいます。このフレットの上の方にボディーに近い方のフレットになればなるほど高い音が出ます。そしてこの間隔はすべて半音で区切られています。
ギターで、仮にドを押さえていてそれを2フレット上にずらして押さえると1音高いレの音になり、さらに2フレットずらすとミに、そしてもう1フレット上にずらすと半音上のファになる、という風に1フレットで半音、2フレットで1音高い音を作るくことができるのです。
開放弦から辿れば、色んな音を鳴らせます。開放弦は太い弦(6弦)から細い弦(1弦)に向かってミ、ラ、レ、ソ、シ、ミと並んでいますので、これを順にやってみましょう。
STEP:3 弦それぞれに音の高さをチェックしよう
一番太い6弦の開放弦は低いミの音です。ミの半音上はファなので1フレットを押さえるとファの音が鳴ります。ファの音の1音上の音がソになるので、1フレットから2つ上の3フレットはソの音になります。さらに2フレット上には1音高いラが5フレットになるわけです。
次に5弦の開放弦はラなので、1音上の2フレットがシ。ドはその半音上なので3フレット。そしてレはその2フレット上なので5フレットとなります。
4弦は、開放がレ。1音上の2フレットがミ。ファはミの半音上なので3フレット。5フレットはソになります。
3弦は、開放がソ。2フレットがラ、4フレットがシ、5フレットがドですね。
2弦は、開放がシ。半音上がドなので1フレットがド。3フレットがレ。5フレットがミになります。
1弦は、6弦と同じミであり6弦より1オクターブ高いミの音です。ミに変わりはありませんので、6弦と全く同じ音の並びになりますので省略します。
このようにして全全半全全全半を覚えて。開放弦の音を覚えていればギターのフレット上の全部の音が分かります。
STEP:4 コードで使われるアルファベットの意味を覚える
では、次に大事なこと。ギターのコードで使用されるA, B, C, D, E, F, Gが何者か理解しましょう。これを知っていると1ランク上がったように感じますね。これは、音の名前すなわちドレミを表しています。ドレミファソラシドの順にアルファベットを並べるとC, D, E, F, G, A, B, Cとなります。Cがド、Dがレ、Eがミ、Fがファです。A, B, Cの順に並べるとAラ,Bシ,Cド, Dレ, Eミ, Fファ, Gソ。これを知っているとかっこいい感じがします。Gと言われたらソだとすぐわかるように覚えましょう。「ラを鳴らしてください」というよりも「Aをください」という方がかっこいいですよね。Aは5弦の開放弦の音でギターの基準的な音なのでAがラだとまずは覚えるといいです。ということで開放弦は太い方からE, A, D, G, B, Eの順にならんでいるというわけです。
これは知っていた!という人も全全半全全全半と一緒に再認識してくださいね。そうするとギターの顔が見えたようで取っつきやすくもなります。それでも数が多いので何回も繰り返してどのフレットに何があるか慣れていきましょう。
STEP:5 5フレットから上はどうなっている?
さきほどの説明では5フレットまでの音を言いましたが、ギターを握って5フレットよりも上の音もたどってみてください。すべてが音階通りの音が出るわけです。フレットの間隔は上に行くにしたがって狭くなりますが、そのようにギターは設計されて1フレット分はすべて半音になっています。上の方のドの音と下の方のドの音がオクターブ違いで同じ音階だということも確認できます。
上の方とは音の高い方、すなわちハイコードの方ですね。さあ、この音の間隔と音の記号を覚えることでハイコードが何でもできるようになりますよ。
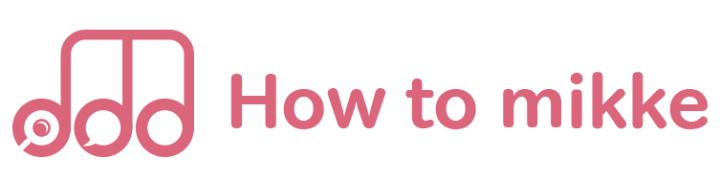


コメント0件