【この記事を書いた人:ソニア】
ピアノの先生。
音楽大学のピアノ科卒業。
中学校教諭一種免許状(音楽)・高等学校教諭一種免許状(音楽)取得。
ピアノの先生解説!音楽に役立つ情報サイト
https://carpediemsoniablog.com/
X(Twitter)
https://x.com/carpediemsonia_
目次
STEP:1 あなたの電子ピアノの「ペダル使い方」は間違っていませんか?
電子ピアノを購入したけどペダルの使い方がよくわからず、困っていませんか?
一番右のペダルを「音を伸ばすスイッチ」としてしか使っていない方が非常に多いのではないでしょうか。
ペダルは、演奏に奥行き、情感、そして豊かな響きを与えるための大切な表現ツールです。
特に電子ピアノのペダルには、アコースティックピアノとは異なる特性があり、その使い方を知らないと、せっかくの電子ピアノの性能を半分も引き出せていない可能性があります。
本記事では、主要検索キーワード「電子ピアノのペダルの使い方」に特化し、3つのペダルの基本的な役割から、演奏が劇的に変わる正しい操作方法、具体的な練習法までを、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。
STEP:2 電子ピアノに付いている3つのペダルの名称と基本的な役割
電子ピアノの3本のペダルのそれぞれの名称と役割を正しく理解しましょう。
1. 右:ダンパーペダル
役割:音を長く伸ばし、響きを豊かにする
使用頻度:最も高い
アコースティックピアノでは、弦に触れているダンパー(消音装置)を全て上げ、弦を解放状態にします。
電子ピアノでも同様に、音の減衰を止め、残響を長く持続させます。
楽曲の和音を繋げたいとき、豊かな響きを出したいときに使用します。
2. 左:ソフトペダル
役割:音を弱く、柔らかく変化させる
使用頻度:中程度
アコースティックピアノでは、ハンマーをずらして弦を1本しか叩かないようにしますが、電子ピアノでは主に音量レベルを下げる(弱音)とともに、音色自体を柔らかいものに変化させる処理を行います。
ただ小さくするだけでなく、感情表現の一つとして使用します。
3. 中央:ソステヌートペダル
中央のペダルは、電子ピアノの機種によって役割が分かれるため注意が必要です。
ソステヌートペダル(高性能な機種に多い):特定の音(ペダルを踏んだ瞬間に鳴っている音)だけを保持し、後から弾いた音はダンパーペダルの影響を受けません。
複雑な曲の表現に使われます。
弱音ペダル(主にアップライトピアノの音を再現する機種):音量を極端に下げるためのペダルです。
アコースティックピアノの夜間練習用の「マフラー(消音フェルト)」の役割を果たし、練習音を小さくしたいときに使います。
STEP:3 【基本編】ダンパーペダル(右)の正しい使い方と「踏み替え」練習
9割の演奏で使うダンパーペダルの使い方こそ、最初にマスターすべきポイントです。
ダンパーペダルの基本操作:和音を繋げる
ペダル操作の基本は「音と音の間を途切れさせずに、滑らかに繋ぐこと」です。
よくある間違いとしては、 音を弾くのと同時にペダルを踏み、和音を変えるときにペダルを上げ下げするなどが挙げられます。
【正しい操作(後踏み)】
和音Aを弾きます。(音を伸ばしたいのでペダルは踏んだまま)
次の和音Bを弾くために、和音Aを弾いた指を鍵盤から離すと同時にペダルをサッと上げます。
和音Bを弾くのと同時(または直後)にペダルを再び踏み込みます。
この「音を離す→ペダルを離す→新しい音を弾く→ペダルを踏む」という一連の動作を、水の流れを止めないようにスムーズに行うのが「踏み替え」です。
【濁りを解消する「踏み替え」のタイミング】
ペダルを適切に踏み替えないと、前の和音の響きが残ってしまい、音が「濁る」原因になります。
正しい「後踏み」を意識するとき、ペダルを上げるタイミングは、新しい和音が響き始めた瞬間です。
この「一瞬のリセット」が、演奏をクリアに保つ秘訣です。
【表現力を高める「ハーフペダル」の使い方】
電子ピアノで「連続検出式」のペダルが搭載されている場合、ペダルの踏み込み量を微妙に調整できます。
これが「ハーフペダル」です。
ペダルを底まで踏み込まず、半分(あるいは1/3)程度で止めることで、音の響きを完全に残さず、しかし完全に切らず、曲に「空気感」や「余韻」を与えることができます。
★活用シーン:静かなフレーズで、音の繋がりのみを確保したいときや、ペダルを深く踏むと濁りすぎる速いパッセージなどで使用します。
★練習法:目を閉じて、ペダルを1/4、1/2、全踏みと段階的に踏みながら、響きの変化を耳で確認する訓練をしましょう。
STEP:4 【応用編】ソステヌート(中央)とソフト(左)の使い方
ダンパーペダル以外も活用することで、表現の幅は大きく広がります。
【ソフトペダル(左):音量だけでなく音色を変化させる】
ソフトペダルは、単に小さな音を出すためだけでなく、「弱く、そして柔らかな音色」にしたいときに使います。
活用シーン:ロマンチックな曲のささやくようなフレーズ、夢の中のようなデリケートな表現など、音色に特別な変化をつけたいとき。
※注意点:電子ピアノの機種によっては効果が限定的な場合もあるため、ご自身のピアノでどのような音色変化があるか、事前に確認しておきましょう。
【ソステヌートペダル(中央):低音だけを響かせる分離術】
ソステヌートペダルは、高度な表現ができます。
まず、長く伸ばしたい低音の鍵盤を指で押さえます。
指を離さずにソステヌートペダルを踏み込みます。
低音の指を離しても、その音だけが伸び続けます。
その間に、ダンパーペダルを踏まずに高音域で細かいフレーズや和音をクリアに演奏できます。
これにより、曲の土台となる低音の響きを保ちながら、上声部を濁らせずに演奏することが可能になります。
STEP:5 ペダル操作でつまずかないためのコツ3つ
ペダル操作でつまずかないためのコツ3つは、以下のとおりです。
①ペダルがON/OFF式か連続検出式か確認する
②足と手の動きを独立させるトレーニングをしよう
③自分の演奏を録音して「濁り」を耳で確認しよう
【ペダルがON/OFF式か連続検出式か確認する】
ご自身の電子ピアノのペダルが、以下のどちらかを確認しましょう。
ON/OFF式:ペダルの踏み込み量が0か100かの2段階(ハーフペダル不可)。
連続検出式:踏み込み量を連続的に検知できる(ハーフペダル可能)。
連続検出式であれば、ハーフペダルを積極的に練習に取り入れてください。
【足と手の動きを独立させるトレーニングをしよう】
ペダル操作は、手が弾くリズムや和音とは独立した動きとして行う必要があります。
練習方法:メトロノームに合わせて、手は単純な和音を一定のリズムで弾き続け、足はそれに合わせて不規則なタイミングでペダルの「踏み替え」だけを行います。この練習で、足の動きが手に引きずられないように訓練します。
【自分の演奏を録音して「濁り」を耳で確認しよう】
ペダルの使い方が正しいかを確認する最も確実な方法は、演奏を録音して客観的に聴くことです。
録音チェックのポイント2つは、以下のとおりです。
①濁りがないか(和音が変わる瞬間に、前の音と次の音が混ざって不快な響きになっていないか。)
②音が切れていないか(フレーズの繋がりがぶつ切りになっていないか。)
「ちょうど良い」ペダルの深さやタイミングは楽譜によっても異なります。
自分の耳を信じて録音で確認しながら調整を続けることが上達への近道です。
STEP:6 まとめ:ペダルは電子ピアノの音を豊かにする鍵
電子ピアノのペダルは、単なる「音を伸ばすスイッチ」ではありません。
正しい使い方をマスターすることで、あなたの演奏は感情豊かになります。
特にダンパーペダルの「後踏み」による正しい踏み替えと、ハーフペダルによる響きのコントロールが、上達の鍵です。
今日から、ペダルに意識を集中した練習を取り入れてみましょう。
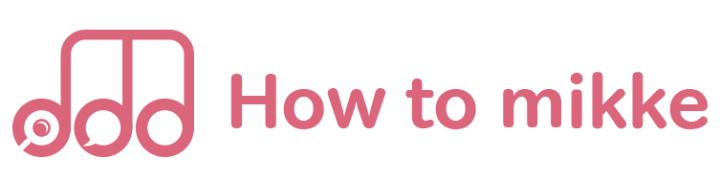
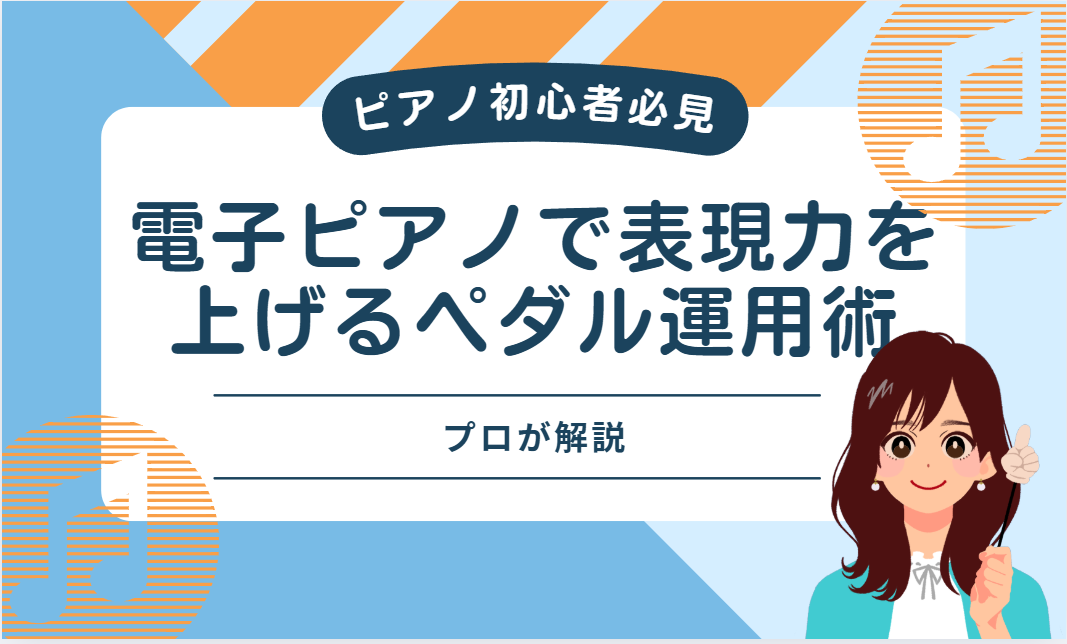

コメント0件