目次
- STEP:1 コードとスケールのステキな関係。
- STEP:2 ドレミ=CDE?!音名を知れば、コードが身近に!
- STEP:3 白鍵だけのコードをおさえてみましょう。
- STEP:4 コード表記のなぞを解こう!
- STEP:5 感じて、気づいて、つながる〜ここから始まるコード進行の旅
- STEP:6 覚えると便利な1451進行をおさえてみましょう。
- STEP:7 90年代の独特の疾走感が魅力〜6451進行
- STEP:8 幻想的な世界観〜4561進行
- STEP:9 数々の名曲を生み出す“カノン進行”〜15634145
- STEP:10 ここで少し寄り道!~Eの響きを感じてみましょう。
- STEP:11 “マルサ進行”でつくる都会派ポップ〜4361 進行
- STEP:12 気持ち揺れ動く「ざらめき」進行?!~1736545
- STEP:13 コードを弾いて感じる「音楽の広がり」
STEP:1 コードとスケールのステキな関係。
「コード進行」は、曲の雰囲気を形作る、音楽の設計図のようなものです。その流れをいくつか引き出しにいれておくと、曲作りや演奏が、より楽しくなります。
はじめに、コードの基礎に触れてみましょう。
画像をご覧ください。これは、Key=C(ハ長調)の音階とコードを順に並べてあるものです。
上の段・ト音記号にはコード(和音)、下の段・ヘ音記号には、スケール(音階)と呼ばれる「ドレミファソラシド」が書いてあります。
実はこのスケールこそが、コードを知るうえで、大事なカギとなります。
STEP:2 ドレミ=CDE?!音名を知れば、コードが身近に!
さて、私たちが馴染み親しんできた「ドレミファソラシド」ですが、実はこれ、イタリア語です。
日本語では「ハニホへトイロハ」、そして、英語では「CDEFGABC」と表します。
コードを読み取るうえでは、この英語の音名を覚えておくことが、とても大切です。ぜひ毎日のように唱えてみることをおすすめします。
「ドレミファソラシド」=「CDEFGABC」ということを知っておけば、コードがぐっと身近な存在になります。
STEP:3 白鍵だけのコードをおさえてみましょう。
下の動画をご覧ください。
https://youtu.be/R9GpnQ5tZVQ
こちらの、Key=C(ハ長調)「Ⅰ」のコード、「C(シー)」から見ていきましょう。
「C」の構成音はドとミとソ。鍵盤でド(Cの音)をおさえ、ひとつ飛ばしで音を3つ重ねると、このCというコードになります。
その次の「Ⅱ」の和音は、同じようにレ(Dの音)から、レ、ファ、ラと音を3つ重ねると出来あがります。このコードは「Dm(ディーマイナー)」と呼ばれます。
そうやって同じように、ミからシの音までをそれぞれひとつ飛ばしに重ねていくと…、7つものコードが出来あがります。しかも、このKey=C(ハ長調)のコードは、すべて白い鍵盤だけで弾くことが可能です。
STEP:4 コード表記のなぞを解こう!
ところで、「あれ…?Cって"ド"って意味じゃないの?」「Dmは、何故、m(マイナー)が付くの?」と思われた方がいらっしゃるのではないでしょうか。そちらについて、少し解説させていただきます。
「C」や「F」「G」という大文字アルファベットのみで表されるコードは、本来「CM(シーメジャー)」「FM(エフメジャー)」「GM(ジーメジャー)」と書かれていたものでした。しかし、この「M(メジャー)」は、「m(マイナー)」と一緒に楽譜上にあると、大変ややこしいのです。そうして、いつしか「M」が省かれ、「メジャーコードは大文字アルファベットのみの表記」ということになりました。
STEP:5 感じて、気づいて、つながる〜ここから始まるコード進行の旅
では、大文字だけのコードを選んで弾いてみてください。…何だか明るい感じがしませんか?
続いて、「m」のついたコードを弾いてみてください。…少し陰のある感じがしませんか?
これが「メジャー」と「マイナー」の違いになります。
さらに、「Ⅶ」のコードである「シ・レ・ファ」Bm♭5(ビーマイナーフラットファイブ)を弾くと、「え…?」と思いませんか?
また、「メジャー」、「マイナー」、「Ⅶのコード」、それぞれを鍵盤でおさえながら、その音と音との幅にも注目してみてください。何か法則性を見つけられましたか?
このように、コードから数々の発見があることがわかります。
前置きが大変長くなりましたが、こうして生まれたコードを並べて作られるのが「コード進行」です。
それらは、楽曲の土台となっています。
それではこれから、いくつかのコード進行について、語らせていただこうと思います。
STEP:6 覚えると便利な1451進行をおさえてみましょう。
コード進行「1451」(Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ)は、音楽の基本となるカデンツ(終止形)のひとつです。曲の始まりと終わりを感じさせる、安定した進行といえます。
この進行は「C(Ⅰ)」から始まり、F(Ⅳ)→G(Ⅴ)→C(Ⅰ)へと戻る流れで、聴いていて“落ち着く”、“帰ってきた…!”と感じる響きです。
ⅠはC、ⅣはF、ⅤはGと、すべてメジャーコードで構成されており、明るく開放的な印象も与えてくれます。
また、動画にあります「転回形」は、文字通り「コードを転回させたもの」です。たとえば、「C」はドとミとソで出来ているということをさっき述べました。この3音という組み合わせが「C」だとわかれば、音をくるっとひっくり返して、「演奏しやすい形」にしても良いのです。そう、Cを「ソドミ」や「ミソド」と弾くことが出来るんです。もちろん、他のコードも同じです。
コードは基本の形だけでなく、転回形をマスターしておくのも、とても良い練習になりますよ。
STEP:7 90年代の独特の疾走感が魅力〜6451進行
コード進行「6451」(Ⅵm-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ)は、いわゆる“小室進行”と呼ばれる有名な進行です。切なさと爽快感が同居するような、ポップスに欠かせない響きが特徴です。
Key=Cでは、「Am(Ⅵm)」→「F(Ⅳ)」→「G(Ⅴ)」→「C(Ⅰ)」の流れになります。マイナーコードから始まることで、少し哀愁を感じさせながらも、最後にCでしっかり明るく締めくくるというバランスの良さが魅力です。
90年代のJ-POPを中心に、多くの名曲で使われてきた進行でもあり、聴くだけで“どこか懐かしい”気持ちになる人も多いかもしれません。ぜひリズムに乗って、この独特の疾走感を感じてみてください。
STEP:8 幻想的な世界観〜4561進行
コード進行「4561」(Ⅳ–Ⅴ–Ⅵm–Ⅰ)は、どこか幻想的で“異世界”を感じさせる響きを持つ進行です。
F(Ⅳ)からG(Ⅴ)へと音が上り、Am(Ⅵm)で一瞬切なさを生み、最後にC(Ⅰ)でふっと光が差すように解決します。
ポップスやアニメソングなど、また、近年の楽曲でも頻繁に登場する人気の進行です。耳なじみがありながらも、どこか夢の中のような、そして、ファンタジーの扉が開くような印象を与えてくれます。
4つのコードを使いますが、音が近いコードを並べているので、比較的演奏しやすい進行です。
STEP:9 数々の名曲を生み出す“カノン進行”〜15634145
クラシック音楽の名曲、パッヘルベルの《カノン》から名づけられたこの進行は、その名の通り「カノン進行」と呼ばれます。
C–G–Am–Em–F–C–F–G(Ⅰ–Ⅴ–Ⅵm–Ⅲm–Ⅳ–Ⅰ–Ⅳ–Ⅴ)は、安定感と感動のバランスが絶妙な“コード進行”です。
GReeeeNの「キセキ」やスピッツの「空も飛べるはず」などの他、数えきれないほどの名曲に使われています。
穏やかに始まり、徐々に心を動かしていくような流れは、まさに“ドラマチックな日常”を感じさせる進行です。
STEP:10 ここで少し寄り道!~Eの響きを感じてみましょう。
これまで、白い鍵盤だけで作れるコードを使った、いくつかのコード進行を見てきました。
ここで、Key=C(ハ長調)スケールだけでは作れない「E(Ⅲ)」コードを登場させてみようと思います。
なぜなら、Eコードは、これからご紹介するコード進行で、重要な役割を持つコードだからです。
Eの構成音は、ミと#ソとシ。Emと同じミから始まりますが、ソの音に#(シャープ)が付きます。
画像では左側がEm、右側がEです。2つを比べて違うところは、「ソ」の音だけです。
たったそれだけのことなのに、コード進行上では、このEにしか出せない魅力があります。特定のコード進行上で「Ⅲ」のメジャーコードが登場すると、明るくも少し色気のある響きに、「はっ」とさせられるかと思います。
それでは、そのE(Ⅲ)に注目しながら、次のコード進行を見ていきましょう。
STEP:11 “マルサ進行”でつくる都会派ポップ〜4361 進行
通称“マルサ進行”と呼ばれているこの進行。
名前の由来は、椎名林檎の名曲「丸の内サディスティック」から来ています。
おしゃれで都会的、それでいてどこか切ない響きが特徴です。
Key=C(ハ長調)では、このマルサ進行に「E」が登場します。
動画を観ていただくと感じていただけるかもしれませんが、「E」のコードが流れると、何だか、ぐっ…ときませんか?
これが、マルサ進行の罠なのです。
実はこの進行…、どんなメロディーでも、おしゃれに変えてしまうという魔力(?)を秘めているとも言われます。ですので、童謡や身近な曲にあてて弾いてみるのも面白くて、大変おすすめです。新しい発見がきっとあるはずです。
STEP:12 気持ち揺れ動く「ざらめき」進行?!~1736545
クリープハイプの『愛のネタバレ』や、『ざらめき』などに使われている「緊張感と解決感が表裏一体!」なコード進行です。この中にも、E(Ⅲ)が登場します。
そのEにもドキッとさせられますが、何よりも2番手である、Bm♭5(ビーマイナーフラットファイブ)の登場のしかたが面白いですよね。
C(Ⅰ)からBm♭5(Ⅶm♭5)への繋がりに、何かしら”不穏さ”を感じたりもします。
それがこのコード進行の良いスパイスになっているとも言えます。
STEP:13 コードを弾いて感じる「音楽の広がり」
いかがでしたでしょうか。
今回は、Cメジャースケールの白鍵コードや、E、Emの違いを踏まえながら、いくつかの代表的なコード進行をご紹介しました。
日常的に触れる童謡からポップスまで、今回の知識を応用すると、曲作りや演奏の幅がぐっと広がります。
お好きなコード進行から気軽に弾いてみて、響きを感じてみてください。
曲を彩ってくれるコードの流れを知ると、練習もどんどん楽しくなること間違いなしです。
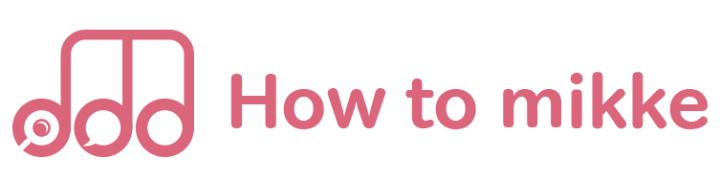


コメント0件