ですが、その単純な演奏にも見方を変えれば多彩な音の表現が可能になります。
今回は和太鼓の演奏で、音の表現の幅を広げたい方の為に、バチの持ち方で音の表現を変える3つの方法をお伝えします。
STEP:1 はじめに
和太鼓のみならず、全ての音は「振動」を介して人の耳に入ってきます。
この「振動」が和太鼓の音に影響を与えますので、そのことを頭に入れて読み進めていただくと、より理解が深まると思います。
STEP:2 バチの持ち方①
小指、薬指支点
まず1つ目は「小指、薬指」を支点にした持ち方です。
音色は「ズシッと重く、深みのある」音が表現出来ます。
そして、この持ち方が和太鼓らしい音を出すのに1番適していると思います。
理由①
人の上半身の神経は、腕から小指の根本につながっている為、力が入れやすく「肩甲骨〜肘〜手首」のエネルギーが1番伝わりやすい。
理由②
持ったバチの支点から、バチ先までが長いので太鼓の鼓面に当たった時バチ先が深く入り込むので、太鼓の振動が大きくなり音に深みが出る。
ただし、欠点もあります。
欠点①
1つ1つの音が重いので、その音ばかりだと聞く側が疲れる可能性がある。
欠点②
複雑なリズムを打つ時に無理に手首を使うことになるので、手首を痛める。
欠点③
鼓面に打ち込んだ時に、バチの振動が止まりやすく、太鼓の鳴り(余韻)が少ない。
以上が「小指、薬指支点」の特徴になります。
STEP:3 バチの持ち方②
親指、人差し指支点①
2つ目は「親指、人差し指」を支点にした持ち方です。
音色は「軽く、明るい」音が表現出来ます。
1つ目に比べ「深み」は劣りますが、太鼓自体の響きが得られ聞く人に心地よさを与えます。
理由①
打ち込んだ後のバチの振動が残りやすく、太鼓の鳴り(余韻)が残りやすい。
理由②
バチを持つ支点からバチ先までの長さが、1つ目より短いので、鼓面に打ち込んだ時に深すぎず自然な響きが得られる。
理由③
打ち込む瞬間に手首ではなく、指で押し出す打ち方なので、手首が痛めにくくなおかつ、複雑なリズムが打ちやすい。
この持ち方にも欠点があります。
欠点①
音が単調になりやすく、深い音が出にくい。
欠点②
打ち込むまでの流れ(肩甲骨〜肘〜手首〜支点)が1つ目より1つ多くなり、エネルギーが伝わりにくい。
以上が「親指、人差し指①」支点の特徴となります。
STEP:4 バチの持ち方③
親指、人差し指②
3つ目は「親指、人差し指」を支点にした持ち方のもう1つの持ち方です。
先に説明した2つ目とは少し違い、手の甲を上に向け親指と人差し指の根本で挟み込む感じで持ちます。
分かりやすくいうと、バチを床に置きそのバチを「親指と人差し指」で挟んだ状態と思っていただくと感覚が掴めると思います。
2つ目と支点は変わりませんが、バチをつまむように持つので、手首をほとんど使わず鼓面に打ち込んだ跳ね返りを利用し複雑なリズムが簡単に打てるようになります。
音色は「軽やかで、跳ねる」音が表現出来ます。
理由①
2つ目より打ち込んだ後のバチの振動が残りやすく、太鼓の鳴り(余韻)が最も残りやすい。
理由②
2つ目とバチを持つ支点からバチ先までの長さが同じだが、鼓面に打ち込んだ時の当たる瞬間が短く、すっきりとした響きが得られる。
理由③
2つ目と同じく打ち込む瞬間に手首ではなく、指で押し出す打ち方なので、手首が痛めにくく「中指、薬指、小指」を使った強弱が出来るので、より複雑なリズムが打ちやすい。
もちろんこの持ち方にも欠点があります。
欠点①
音が明るく、深い音が出にくい。
欠点②
打ち込んだ後の跳ね返りの感覚を掴むことと、指で送り出す感覚を掴むのに時間がかかる。
欠点③
打ち込むことが難しく、慣れないうちは鼓面の表面しか響かず、音が細くなる。
以上が「親指、人差し指②」支点の特徴となります。
STEP:5 終わりに
和太鼓は団体によって持ち方が決められているところも多いと思います。
個人的にはせっかく和太鼓をしているなら、音の表現にもこだわって、バチの持ち方なども使い分けると、いつも演奏している曲が一味違って聞こえるのでは無いかと思っています。
是非、今回紹介した持ち方を実践していただきそれぞれの団体に良い影響が出れば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
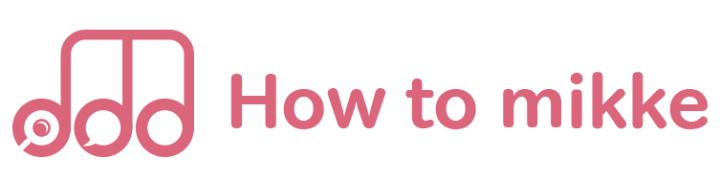


コメント0件