「もっと表現して!と先生に言われたが、よく分からない」
「自信を持って表現したい!」
ピアノ演奏では、表現をしましょうと言われることがしばしばあります。
なぜ、表現をつけなければならないのでしょうか。それは、自然な表現のある演奏は聴き手にとって心地よい演奏になるからです。レッスンや発表会で「良い演奏でしたね」と声を掛けられると、ピアノを継続する励みになりますね。今回は現役ピアノ講師の筆者が、初心者も今すぐ実践できる、強弱をはじめとした自然な表現をつけるコツを3つご紹介します。ぜひ、最後までお読みくださいね。
目次
STEP:1 強弱とは?表現の第一歩、音量のコントロール
「強弱を付けましょう。」ピアノ学習者であれば誰もが一度は言われたことのあるセリフではないでしょうか。自分では音の強さを変えて表現をしているつもりでも、聴いている方には印象を与えられないことがあります。さて、その原因は一体何なのでしょうか。
STEP:2 コツ①自分が弾いた音を聴く
常に音は聴いていると思われた方が多数かと思いますが、自分の出したその音、本当に聴けていますか?ここで、ピアノを使って音量の変化を体感してみましょう。動画で紹介しますが、2つの動画の音量は変えず比較してください。今日は大まかにf(フォルテ)と、p(ピアノ)をご紹介します。ご自宅のピアノでも実践してみてくださいね。
f フォルテ:強く
【動画】フォルテ
p ピアノ:弱く
【動画】ピアノ
音量の差は具体的に数値化されていませんので、ご自身の耳の感覚でfとpを作ることが大切です。はっきり、分かりやすく音量を変えてみてください。強く弾こう、弱く弾こうと気持ちも一緒に変化させると弾きやすいです。
STEP:3 コツ①おまけのポイント
楽譜上に強弱記号で音量の指示があった場合は、次の指示までは、基本的にその音量のまま演奏を続けると良いです。曲のレベルが上がると、次のフレーズへの向かい方が複雑だったり解釈の違いから様々な表現が生まれることがありますが、まずは基本を抑えることが大切です。
STEP:4 コツ②指先のタッチを変える
次は指先のタッチです。今回は、指の形の解説は割愛させていただきます。レッスンに通われている方は、講師に「指の形はどうですか?」と質問してみると良いです。また、自分が弾いている姿を鏡に写し、定期的にフォームを確認するのも効果的ですよ。
さて、鍵盤に直接触れる指先ですが、鍵盤にかかる重みを意識されたことはありますか?
先ほどfとpの変化を作りましたが、今度は指先の意識も加えてみます。
曲想によって表現が変わることは前提とし、音量変化の作り方のコツとして解説します。
f(フォルテ)のタッチ:指先に重みをかけ、強い音を出します。指先は少し潰れ、白くなります。慣れている方は、腕や体の重みを指先に乗せてみましょう。できるだけ、脱力します。
【指先画像】
p(ピアノ)のタッチ:指の形は保ったまま、指先の重みがfより少なくなります。
【指先画像】
強弱をつけることを前述しましたが、実際は鍵盤に接地する指先のタッチをコントロールします。強弱の変化を耳で意識し、さらにタッチにも注意を向けることで、音楽がより自分のものとして感じられるようになるでしょう。曲中に強弱を設定し、きちんと実践するだけでも自然な表現をつけることができますよ。
STEP:5 コツ③フレーズを意識する
音楽はフレーズと言って、旋律をひとまとまりで捉えることができます。楽曲により異なりますが、4小節や8小節で構成されていることが多いです。残念ながら、フレーズは楽譜に明記されていませんので、今回はブレス(息継ぎ)を使ってフレーズを自然に表現する方法を解説していきます。
文には文節があるように、音楽にはフレーズがあります。
たとえば「おはようございます、今日もいいお天気ですね。」と挨拶するとしましょう。
様々な言い方が思い浮かぶと思いますが、大きく3つの部分に分けられます。
1.「おはようございます」:一息で言います。
2.「、」:息継ぎをします。
3.「今日もいいお天気ですね。」:文は終わりに向かい、まとめとなります。
抑揚をつけると、印象に変化が生まれますね。音楽も文章のようにフレーズを設定をすることが大切です。きらきら星の楽譜にスラーとブレス(V)でフレーズを記入してみます。
【楽譜画像】
Aは一息で、V(ブレス)は鍵盤から指を離し、一瞬音を無くします。
BもAと同様に一息で演奏します。B終わり、メロディの「ド」音はぶっきらぼうにならず、優しいタッチで弾けると素敵ですよ。「A→ブレス→B」で一つのフレーズが出来上がりましたね。
このように、楽譜にはフレーズが隠れています。ゆっくりメロディーだけを演奏し、フレーズ探しをしてみてはいかがでしょうか?グッと表現が深まりますよ。
STEP:6 まとめ:強弱が付かない原因と対策
ここまで、ピアノで自然な表現をつける3つのコツを解説させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?強弱の変化が付かない原因を以下にまとめます。
・自分の演奏を聴くための、耳を深く使えていない
・強弱の幅の設定が狭い
・指先のタッチを意識できていない
・なんとなくフレーズの表現をしている
今回ご紹介した3つのコツを演奏に取り入れることで、すぐに表現の幅を増やすことができます!早速お試ししてみてはいかがでしょうか。自分の演奏を聴く力、そして指先のタッチの感覚を研ぎ澄ますこと。これらはピアノ演奏の根っこの部分にあたると筆者は考えます。強弱やフレーズに限らず、常に意識ができると課題の早期発見・解決の強い味方になること、間違いなしですよ!
最後に、ピアノ演奏する上で大切と言えるのは、奏者が音楽に心動いていることです。表現が気に入らず、変になっても心配する必要はありません。心の移ろいとスキルを掛け合わせ、あなたにしかできない、素敵な音楽を紡ぎ出してくださいね!最後までお読みいただきありがとうございました。
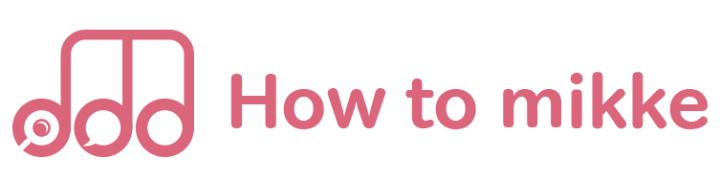
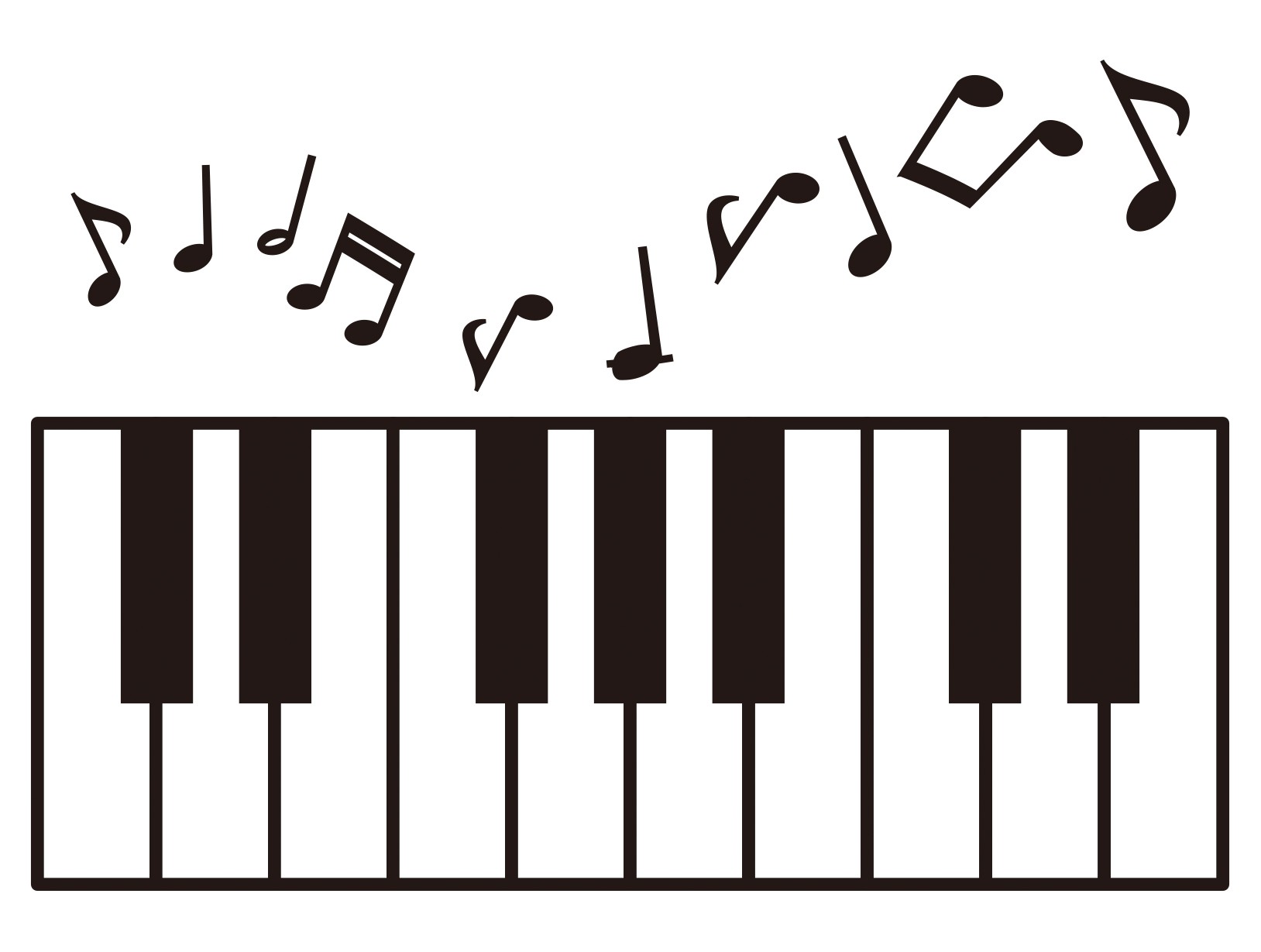

コメント0件