ピアノが苦手でも簡単なアレンジを行うことで、ピアノの伴奏は可能です。
本記事では、保育現場でのピアノ伴奏経験を持つ筆者が、保育現場でのピアノ伴奏の大切さ、誰でも簡単にピアノを弾ける伴奏アレンジのコツを紹介します。
本記事を参考にピアノ伴奏に対する苦手意識を克服しましょう。
目次
STEP:1 保育現場でのピアノ伴奏について
保育現場においてピアノ伴奏は必要不可欠です。
季節の歌や手遊び歌など、日常的な伴奏はもちろん、発表会や卒園式などの大切な行事でも伴奏が求められます。
歌を歌うことは、子どもたちの言葉、発達、リズム感の習得をサポートしています。歌を歌う際に、伴奏があると、子どもたちは歌いやすさを感じ、楽しい雰囲気作りが可能です。
ピアノ伴奏は、子どもたちの活動や経験を広げる重要な役割を担っています。
STEP:2 ピアノ伴奏で大切なこと
ピアノ伴奏を行う際は、途中で間違えてしまっても伴奏をやめず、最後まで弾き続けましょう。
伴奏中に「1音を外してしまった」「和音を間違えた」などのトラブルは比較的よくみられます。筆者も、演奏時に間違えてしまった経験は多々あります。
しかし、一度伴奏が止まってしまうと子どもたちは混乱してしまい、途中からの再開はハードルが高いです。
特に式典では演奏の一時中断は時間も取られ、雰囲気を損なう可能性があります。
伴奏を止めずに、そのまま修正できれば、雰囲気を乱すことなく、子どもたちもそのまま歌を続けられます。
もし、ミスをしてしまっても焦って伴奏をやめず、弾き続けるよう意識しましょう。
STEP:3 簡単に弾ける伴奏アレンジのコツ3選
ピアノ伴奏が楽譜通りしっかりとできなくても問題ありません。どんな曲でも、簡単に伴奏ができるアレンジ方法を3つ紹介します。
音符、和音の一番上の音だけ弾く
複雑な音符は避けて弾く
コードを覚える
それぞれの弾き方について「大きな栗の木の下で」の楽譜をもとに具体的に解説します。
STEP:4 参考資料
STEP:5 音符、和音の一番上の音だけ弾く
和音は、複数の音を同時に押さえる技術が必要であり、単音より難しさを感じやすいです。
例えば、参考譜面のCやFのような和音は、Cのドミソの「ソ」、Fのドファラの「ラ」の音を弾くだけで伴奏が可能です。
その際、右手の音とタイミングを合わせて弾くことが重要です。楽譜を縦に見て、どのタイミングで音を弾くのか確認しましょう。
右手と左手のタイミングが合っていれば、和音が単音になっても、演奏に問題はなくスムーズに伴奏が可能です。
STEP:6 1小節ごとのメロディの最初の音を弾く
各小節の右手の音を左手で弾いてみましょう。
楽譜の縦線で区切られているところが、1小節となります。
「おおきな」と始まる部分では、メロディを弾く右手が「ド」で始まりますので、左手も「ド」
「くりの」の部分は、右手は「ミ」なので、左手も「ミ」というように、先述した通り一音だけでも伴奏になります。
自分が弾きやすいように工夫しながら弾きましょう。
STEP:7 コードを覚える
コードを覚えると、すぐに伴奏でき、弾ける曲数も増やせます。
ただ、メジャーコードやマイナーコードなど、基本のコードだけでも全24種類あり、覚えるまでに時間がかかります。
今回の参考にした「大きな栗の木の下で」の楽譜で使うコードは
C ドミソ
F ドファラ
G7 シレソ
Em ミソシ
です。
どの楽譜にもコードが書かれており、コードを覚えていると複雑な音符が書かれていても、そのコードの和音を弾くことで、伴奏ができます。
コードを覚えることも、伴奏をすばやくアレンジするコツです。
STEP:8 まとめ
以上、簡単に弾ける伴奏アレンジのコツについて解説しました。
保育現場においてピアノ伴奏は必要なものではありますが、ピアノが苦手でもアレンジをすることで、簡単に曲を弾くことができます。
初めから和音や複雑な音を弾けなくても_まずは一音から伴奏を行い、音符の数を増やしていくことがポイントです。
また、アレンジを取り入れて、多くの曲を伴奏できると現場での活動の幅も広がります。
アレンジを導入して、ピアノ伴奏への苦手意識を減らしていきましょう。
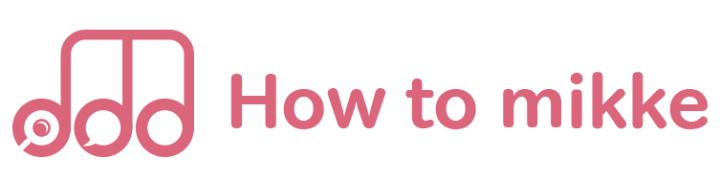


コメント0件