ここでは「4分ストローク」「8ビート」「カッティング入り8ビート」「アルペジオ」の順に紹介します。
C/F/Gの3つのコードでも、右手のリズムパターンを変えるだけで飽きずに楽しめます。
それぞれのステップに演奏動画も載せているので、動画を見ながら一緒に弾いてみて、リズムの感覚をつかんでみましょう。
目次
STEP:1 まずは基本の4分ストローク
4分ストロークは、最もシンプルな弾き方です。
1小節に4拍あると考えて、1拍ごとに弦をダウンストローク(下に向かって弾く)で弾くパターンです。
歌いやすくリズムが安定するので初心者にオススメです。
弾き方の説明
1.左手でコードを押さえる(例:Cコード)
2.右手は弦の上で軽く手首を動かし、下方向に弦を弾く
3.1拍につき1回弾き、1小節で4回弾く
4.最初はゆっくりでOK。リズムが安定したら曲に合わせてスピードを上げる
基本の4分ストロークに慣れたら、次はリズムに変化をつけてみましょう。ここから紹介するパターンを取り入れると、一気に演奏が楽しくなります。
図解と動画を載せますので参考にしてください。
STEP:2 8ビートでノリを出す
8ビートはダウン・アップを交えた定番パターンの弾き方です。
ノリが出て、より弾き語りらしさが増します。
最初は弾きながら歌うのが難しいかもしれませんが、ゆっくり弾きながら歌うのを繰り返してみましょう。
まずストロークだけで練習して、慣れたら歌をのせる流れがオススメです。
弾き方の説明
1.左手でコードを押さえる(例:Cコード)
2.右手は親指と人差し指を軽くくっつけてダウン、ダウン、アップ、空振りダウン、アップ、ダウン、アップ
休みをサボらず空振りするのが大切で、ここを省略すると全体がずれてしまいます。
図解と動画を載せますので参考にしてください。
補足:リズムを数えるときに出てくる「&」は、拍と拍の間の“裏拍”を表します。
1小節を「1 2 3 4」と数えると拍の頭(表拍)しかありませんが、実際にはその間にもリズムがあります。
そこで「1と2と3と4と」と数えると、自然に8つに分かれます。
英語ではこの「と」を「&(アンド)」と表記し、
1 & 2 & 3 & 4 &
(読み方:ワン・エン・ツー・エン・スリー・エン・フォー・エン)
のように数えます。
この「&」のところにストロークを入れると、自然に8ビートらしいノリが出てきます。
STEP:3 カッティングでリズム感アップ
8ビートのストロークに「チャッ」という音を混ぜてアクセントをつける弾き方です。
「チャッ」という音は、前の音を弾いた後にすぐ親指の内側で弦を軽く押さえて弾くと出ます。
「チャッ」という音の出し方には諸説あります。ここでは筆者がやりやすい方法を紹介しましたが、
他にも親指だけで押さえる方法や、手のひらの側面で軽く弦を触れる方法などがあります。
自分が弾きやすい方法を試してみてください。
最初はうまく「チャッ」という音が鳴らないかもしれませんが、あきらめずに何度も練習してみましょう。
弾き方の説明
1.左手でコードを押さえる(例:Cコード)
2.右手は親指と人差し指を軽くくっつけてダウン、チャッ、アップ、空振りダウン、ダウン、チャッ、アップ
図解と動画を載せますので参考にしてください。
STEP:4 アルペジオで雰囲気を変える
アルペジオは和音の構成音を同時に鳴らさず、一音ずつ順番に鳴らす弾き方で、「分散和音」とも言います。
同じ曲でも弾き方をアルペジオにするだけでガラッと印象が変わりますよ。
指使いの基本パターンを説明します。
弾き方の説明
1.左手でコードを押さえる(例:Cコード)
2.右手の親指で4弦、中指で1弦を同時に鳴らす→親指で3弦、人差し指で2弦、親指で3弦
1小節でこの動きを2回繰り返すとリズムが安定しやすく、曲に合わせやすくなります。
最初はゆっくりのテンポで練習し、手の動きを覚えることを優先しましょう。
図解と動画を載せますので参考にしてください。
STEP:5 1小節に2つのコードがあるときの切り替え方
曲の中には、1小節に2つのコードが入るパターンもあります。例えば「C → G」といったコード進行です。
この場合も右手は止めず、リズムを崩さずに左手のコードを切り替えるのがポイントです。
4分ストロークの場合
1小節を4拍と考え、前半2拍をコードA(例:C)、後半2拍をコードB(例:G)で弾きます。
拍 1 2 3 4
コード C C G G
右手は1拍ごとに弦をダウンストロークするだけなので、リズムを止めずに左手のコードを2拍目と3拍目の間で滑らかに切り替えます。
空振りのタイミングで切り替えると、より自然につながる音になります。
8ビートの場合
1小節を4拍と考え、ダウン・アップを組み合わせた8ビートで切り替える場合も同じ考え方です。
例えば「C → G」の場合、前半2拍をCコードで、後半2拍をGコードで弾きます。
右手は「ダウン・ダウン・アップ・休み・アップ・ダウン」のリズムを崩さず動かし、左手は拍の切れ目でコードを滑らかに切り替えます。
前半(Cコード):ダウン・ダウン・アップ・休み
後半(Gコード):アップ・ダウン・(必要に応じてアップ)
ポイントは、右手のリズムを止めないこと。コードを切り替える瞬間も空振りや休みのタイミングを使うと、音が途切れず自然につながります。
アルペジオの場合
1小節を2つに分け、前半のアルペジオをコードA、後半のアルペジオをコードBで弾きます。
例えば「親指→4弦、中指→1弦、親指→3弦、人差し指→2弦、親指→3弦」を1回のアルペジオとすると、1小節で2回繰り返す中でコードを切り替えます。
右手は動かし続け、左手はコードを滑らかに移動させることで、途切れず自然につながる音になります。
STEP:6 まとめ(きらきら星を4つのリズムで弾き語り)
3コードでも右手パターンで雰囲気を変えられます。
好きなパターンを1つずつ練習して、曲に合わせて使い分けてみましょう。
1つの曲でもAメロはアルペジオ、サビは8ビートなど、右手のパターンを切り替えるだけでアレンジの幅が広がります。
録音して聞き返すと成長がわかりやすいです。
単純なコード進行でも、右手次第で「自分らしい演奏」に変わるので、ぜひ挑戦してみてください。
最後に、きらきらぼしを曲の中で弾き方を替えながら通して演奏してみた動画をのせておきます。
参考にしていただければ幸いです。
一緒にウクレレを楽しみましょう!
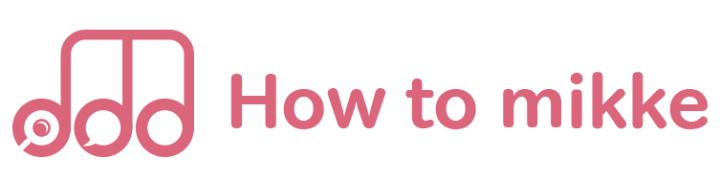


コメント0件