今回、ピアノでよく使われる基礎奏法を3つ解説しますので、ぜひ最後までチェックして基礎奏法をマスターしましょう。
目次
STEP:1 ピアノの基礎奏法
今回ご紹介するピアノの基礎奏法は以下の3つです。順番にみていきましょう。
1.指づかい
2.アルペジオ
3.ペダル
STEP:2 指づかい|指番号
ピアノには指づかいがあります。左右の5本の指番号を覚えましょう。
・親指ー1番
・人差し指ー2番
・中指ー3番
・薬指ー4番
・小指ー5番
STEP:3 指づかい|基本準備
正しい指づかいをすると、演奏がスムーズになったり、無駄な力が入らず無理のない演奏に近づけます。まずは楽譜の運指(指番号)に従うとよいでしょう。
運指は音符の上に番号で記載されています。
たとえば、下記の楽譜を右手で弾く場合、ドに1番の指をセットし、次に2番の指をレ、3をミ、4をファ、5をソに置きます。1つの鍵盤に1本ずつ指が置かれている状態で運指基本の準備ができました。鍵盤に置かれている指で演奏します。
STEP:4 指づかい|広げる・くぐらせる
指づかいの基本奏法で広げたり、くぐらせるテクニックがあります。
下記の楽譜を右手で演奏する場合、ド→ミを1ー2の指で弾くことで、鍵盤が1つ飛ばしとなり、指を広げるテクニックを使っています。
次にファ→ソを3ー1で弾くためには、1の親指を3の中指の下からくぐらせます。くぐらせるテクニックは、5本の指におさまらない音域の演奏が必要なとき、スムーズな演奏効果が得られます。
STEP:5 アルペジオ|装飾
アルペジオとは?和音(コード)を構成する音を分散させて弾く奏法です。分散和音とも呼ばれます。
音の装飾として使われるアルペジオには、2つのパターンがあります。
・上行
・下行
楽譜には画像のような波線の演奏記号で記され、左が上行、右が下行です。
上行は和音の下から上に向かい、1音ずつ音を積み重ねていきます。下行は反対に、上から下に音を重ねます。
力まず手首の力は抜き、音が抜けないように、1音ずつ聴きながら弾きましょう。初めはゆっくり練習し、だんだん早くし、指定の音価を目指します。
STEP:6 アルペジオ|伴奏
伴奏でもアルペジオ(分散和音)がよく使われます。
指が転がりやすく、テンポが早くなりやすいので気をつけましょう。今回は4拍子のアルペジオを一例に挙げましたが、拍子やリズムにより様々なアルペジオの形があります。
STEP:7 ペダル|フォーム
ペダルを使うと表現の幅を広げることができます。
通常ピアノには3本のペダルがついていて、足で操作します。かかとは地面につけ、足の裏、親指の付け根がペダルに接地するようにフォームを作ります。かかとが浮かないように注意しましょう。
STEP:8 ペダル|ダンパーペダル(右)
一番右のペダルはダンパーペダルで、一番よく使うペダルです。
ダンパーペダルを踏むと、鍵盤から指を離しても音が伸びます。踏みかえのタイミングは楽譜に合わせすぎず、耳で音の濁りを感じた時に踏みかえすると良いでしょう。
STEP:9 ペダル|ソステヌートペダル(中央)
中央のペダルはグランドピアノ・電子ピアノと、アップライトピアノで効果が変わります。順番に解説します。
◾️グランドピアノ◾️電子ピアノ
ソステヌートペダルといい、ペダルを踏んだ瞬間の音だけを持続します。主にクラシックの上級曲で使われる他、奏者の判断で使われますが出番は少ないです。
◾️アップライトピアノ
マフラーペダルといい、家庭用消音機の役割があります。ペダルの横に窪みがあり、引っ掛けたまま演奏すると楽器全体の音が小さくなります。
STEP:10 ペダル|ソフトペダル(左)
左のペダルはソフトペダルです。
ソフトペダルを踏むと音が優しく、丸くなります。
楽譜にuna corda と書かれている時にソフトペダルを踏み、tre corda で離します。
または奏者の判断で使用もできます。
STEP:11 まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はピアノの基礎奏法3つをご紹介させていただきました。
基礎奏法を習得することで、演奏の幅がぐんと広がります。
また、ピアノの練習をするとき、どんな基礎奏法(テクニック)が使われているのか?意識を持つとより質の高い練習に近づけますよ。これからもピアノを楽しみましょう!
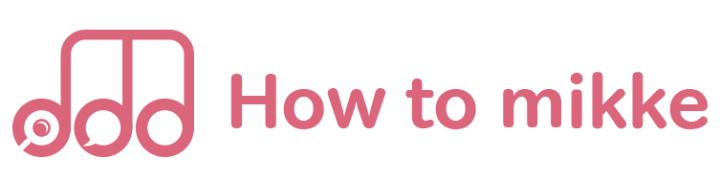
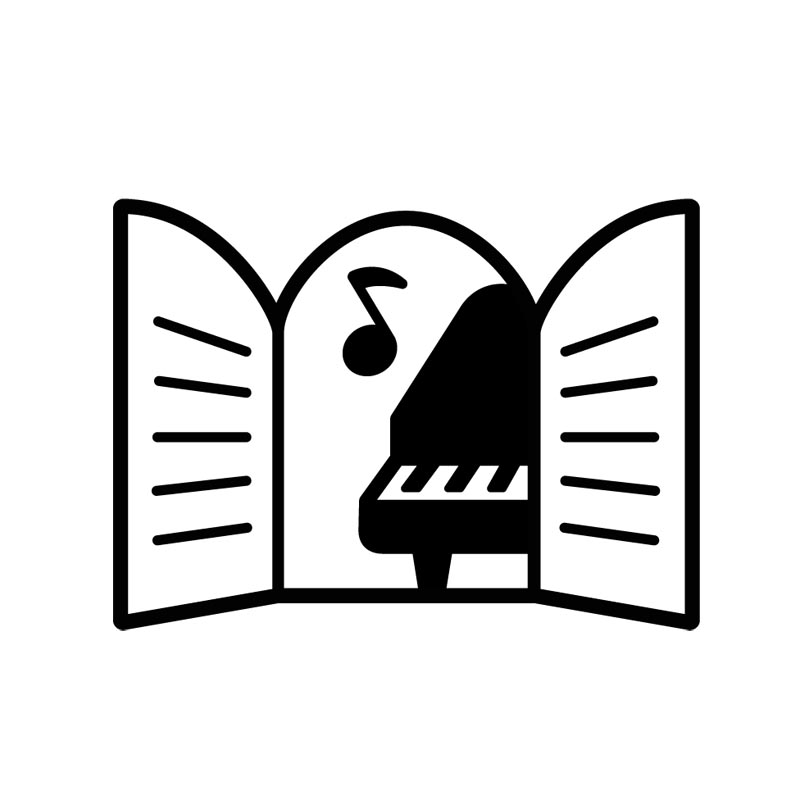

コメント0件