最初のハードルとなるのが「バチの持ち方」。
見よう見まねで握ってみたものの、「これで合っているのかな?」と不安に感じたことはありませんか?
この記事では、初心者の方でも安心して練習できるように、バチの持ち方を基本からやさしく解説していきます!
STEP:1 1. バチってどんなもの?
三味線の演奏では、ほとんどの曲でバチを使います。
一部の流派やスタイルでは、ピックや爪弾き(つまびき)で演奏することもありますが、基本的にはバチで三本の糸を弾き分けるのが前提です。
「バチ」は漢字で「撥」と書きます。
撥にはさまざまな種類があり、流派・演奏ジャンル・手の大きさ・好みなどによって、形や重さ、素材が異なります。
素材だけを見ても、木・プラスチック・アクリル・鼈甲・象牙など、さまざま。
ここでは、初心者の方でも手に入りやすく扱いやすい「プラスチックの撥」を使って説明しますが、基本的な持ち方・弾き方は共通です。
⸻
バチの各部の名称
三味線のバチ(撥)は、イチョウの葉のような形をしています。
太くしっかりした「才尻(さいじり)」から、薄く広がった「撥先(ばちさき)」に向かって開いたかたちです。
《各部の名称》
• 撥先(ばちさき):弦に当てる尖った部分
• 開き(ひらき):撥先の広がった面
• 才尻(さいじり):撥のお尻の部分(握る方)
STEP:2 2. バチの持ち方
それでは、実際に撥を持ってみましょう!
⸻
① 小さく前へならえ
まず、右手をお腹の前に出して、「小さく前へならえ」の形をとります。
指はまっすぐ揃えておきましょう。
⸻
② 小指を広げる
薬指と小指の間を軽く開きます。
うまく広がらない場合は、力を抜くだけでも大丈夫です。
⸻
③ 左手で撥を持ち、右手に差し込む
左手で撥の「開き(ひら)」部分を優しく持ちます。
このとき、撥の面(広がっている方)は床と平行にしてください。
そのまま、右手の薬指と小指の間に撥を差し込みます。
差し込むのは撥の全長の1/3程度、才尻(太い方)側です。
奥まで差し込まず、少し空間が残るくらいがちょうど良いです。
⸻
④ 人差し指・中指・薬指で握る
撥を差し込んだ状態のまま、手のひらを床に向けて返します。
そして、人差し指・中指・薬指で撥の柄(え)を優しく支えます。
このとき、ぎゅっと握らず、3本の指を添えるだけでOK。指先はできるだけ揃えましょう。
⸻
⑤ 親指を立てる
親指と人差し指の間で三角形を作るような形になります。
親指は、撥のカーブに沿うように軽く立てて添えます。
⸻
⑥ 手首を返す
最後に、手のひらを自分のお腹に向けるように手首をぐっと曲げます。
手の甲と腕が90度くらいになっていればOKです。
⸻
📽️ 文章ではイメージしにくいかもしれませんので、以上の1〜6の手順を動画にまとめました。ぜひ参考になさってください!
STEP:3 3. 三味線を叩いてみよう!
撥が持てたら、さっそく三味線を叩いてみましょう。
まずは三の糸(一番細い糸)の開放弦(何も押さえない)を叩く練習から始めてみます。
⸻
【気をつけるポイントは3つ】
1. 撥の角度
→ 撥は、
①胴の表面に対して35〜45度の角度を維持します。
②撥の開きと三味線の枠が平行になるように構えます。才尻が上がらないように注意しましょう。
2. 手首の角度
→ 腕と手のひらが直角になるように手首を曲げます。手首の角度は固定!
腕全体を持ち上げるのではなく、手首を返して撥先を糸と太鼓に打ち付けます。
団扇をパタパタとあおぐイメージです。
3. 当てる場所
→ 撥先を半円型の撥皮(ばちかわ)部分にしっかり当てましょう。
実際の撥の動き方や手首の返し方は動画でご確認ください。
STEP:4 4.まとめ
はじめのうちは撥がうまくあたらなかったり、音が鳴らなかったり、撥が空振りしてしまったり…
でも、それは誰でも通る道です。焦らず、少しずつ「手に馴染む感覚」をつかんでいきましょう!
⸻
まとめ
三味線の「バチの持ち方」は、音を出すための基本中の基本。
正しく持てるようになると、音も安定して、演奏がずっと楽しくなります。
大事なのは「力まず、正しい角度と支え方を意識すること」。
繰り返し練習して、少しずつ自分の手になじませていきましょう。
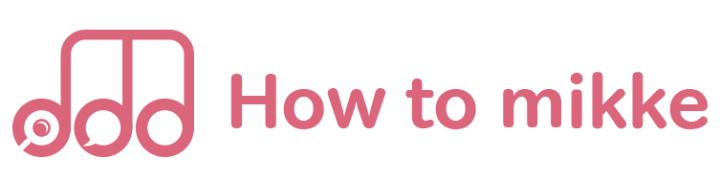


コメント0件