でも、いざ取り掛かろうとすると「ベースラインって難しそう…」と思うかもしれません。
僕自身もそう感じていましたが、紐解いていくと最初はシンプルなものでOKなんです。
シンプルながらも基本を丁寧に重ねていくことで、自然と“プロっぽさ”が身についていきます。
今回は、ベースを始めたばかりの方でも必ず弾けるようになる「プロっぽく聴こえるベースラインを作るための3つのポイント」を紹介します。
ルート音を中心としたシンプルな構成からスタートし、3度・5度の使い方やリズムの工夫、つなぎの音(パッシングノート)による滑らかな動きまでを丁寧に解説しており、「プロっぽく聴こえる」ための実践ポイントを3つに絞って解説しているので、演奏初心者でもすぐに取り入れられる内容となっています。
「なんとなく弾く」から「理由を持って弾く」へ、一歩進みたい方におすすめの内容です。
目次
STEP:1 ポイント1:ルート音を軸にする
ベースラインの役割は、曲の中でコードの土台を提示することです。
コードを理解するために、まず基本中の基本として、コードの「ルート音(根音)」を覚えましょう。
たとえば「Cコード」であれば、ルートは「C(ド)」です。
初心者のうちは、1拍目や小節の頭でルート音を鳴らすだけでも、曲全体が安定して聴こえるので、意識するようにしましょう。
・まずはルート(CコードであればC)だけでOK!
・他の音を弾く前に、ルートを外さない(小節の頭に C, G, A, F を置く)意識を持つとグッと良くなります。
STEP:2 「3度」を加えてみよう
ルートに慣れてきたら、同じコードの中にある「3度」を加えてみましょう。
例えば、Cコード(メジャー)は明るい響きで、Cに対して3度の「E」を使います。
Cmコード(マイナー)はちょっと暗くて、メジャーの時に使っていたEを半音下げてE♭(短3度)を使います。
この音の使い方が、明るい/暗いを決めるポイントです。
STEP:3 「5度」を加えてみよう
5度(例:CコードならG)は、響きに安定感を持たせる音で、ルートとの組み合わせにもよく使われます。
STEP:4 ポイント2:リズムを意識して「ノリ」を出す
どんなに音選びが正しくても、リズムがヨレていたらプロっぽくは聴こえません。
逆に言えば、ルートだけでもリズムにノリがあればカッコよく聴こえるのがベースの魅力です。
ここではジャズ(4ビート)、ボサノバ、R&Bでよく使われるベースラインを例に、それぞれの特徴を解説します。
STEP:5 4分音符でドライヴ感を出す(ジャズの4ビート等)
「1小節に4つ音が入る」ので「4ビート」と言います。
一見、単純な弾き方に見えるかもしれませんが、ジャズにおけるベースの役割は「弦を力強く振動させて(※力任せに弾く、ということではありません)スウィングしながらグイグイと進む」つまり「ドライヴ感」を持ってバンド全体を牽引する重要な役割があります。
練習すればするほど奥深い世界なので、ぜひ取り入れてみてください。
STEP:6 8分音符と休符を使ってノリを出す(ボサノバや多くのラテン等)
ボサノバや多くのラテン音楽においては、ベースは4ビートと同じように、あるいはそれ以上に重要視されるリズム楽器です。
この基本の動きをしっかりと身につければ、ジャムセッションやライブで「ハーモニーとリズムを結合する」というベースの醍醐味を楽しめますので、しっかり身につけるようにしましょう。
STEP:7 シンコペーションでグルーヴ感を出す(ファンクやR&B等)
R&B等のゆったりした曲やポップスにおいてもベースがハーモニーとリズムを結合することに変わりはありません。
その中で「ベースラインに一定の法則性を持たせて曲の雰囲気・流れを作り出す」ことができるのもベースの役割の一つですので、様々な音源を聴いて吸収してみましょう。
STEP:8 ポイント3:つなぎの音(パッシングノート)を使って滑らかに
コードの構成音(ルート、3度、5度)だけでも十分ですが、少しずつ「つなぎの音」を加えることでよりプロっぽいベースラインになります。
これはパッシングノートと呼ばれるもので、コードとコードの間を滑らかにつなぐ役割を持ちます。
実際に弾く時、半音や全音を使ってステップアップ・ダウンするようなラインを入れると、動きが出て滑らかになります。
ポイントは「次のコードに向かって解決する」こと。
無理に難しい音を入れるよりも、次のコードにうまくつなげることを優先しましょう。
練習の際は、ドラムのリズムトラックやメトロノームを使って、タイミングに気を配るのがおすすめです。
シンプルなラインを、安定して心地よく鳴らすことが何よりの近道です。
STEP:9 まとめ
初心者がベースラインを作るときは
・ルート音を中心に考える(慣れたら3度・5度も)
・リズムでノリを出す
・つなぎの音で滑らかさを出す
この3つを意識するだけで、驚くほど「プロっぽく」聴こえるようになります。
最初はシンプルな構成から始めて、少しずつ音の選び方やリズムのバリエーションを広げていきましょう。
ベースは「少ない音でバンドの屋台骨を支える」奥深い楽器であると同時に、演奏者のセンスや意図がバンド全体に強く反映される重要なパートです。
焦らず、じっくり育てていきましょう。
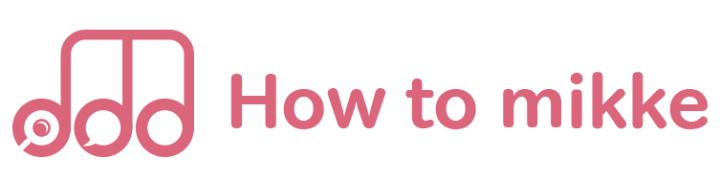
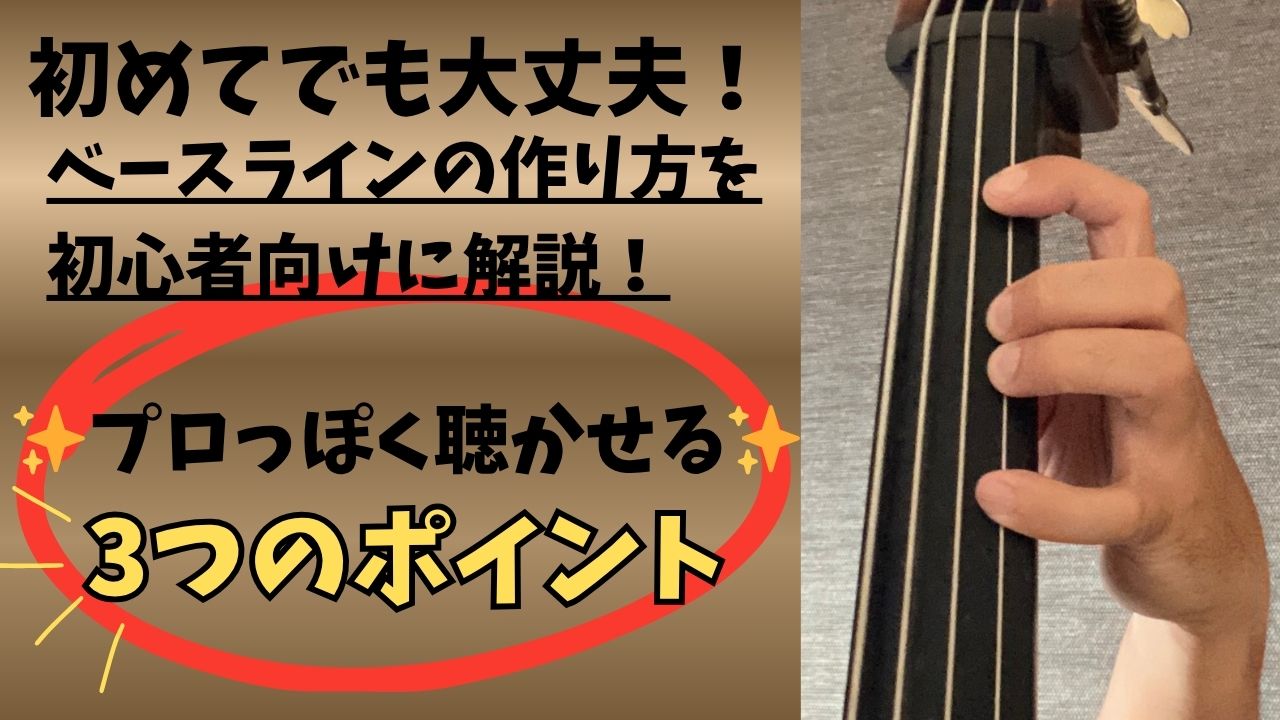

コメント0件