単に力強く弾くのではなく、効率的に弦の振動を引き出すためのフォームや重力・握力の活用法、アポヤンド奏法の重要性、右手位置による音質コントロールなど、初心者から中級者まで役立つ内容を幅広く紹介。
さらに、効果的な練習方法も提示し、即実践できる構成となっています。
目次
STEP:1 はじめに
「なんとなく音が軽い」「もっと太くて芯のある音を出したい」
そんな悩みを抱えているベーシストは少なくありません。
個人練習の時は気にならないけど、バンドやセッションに参加すると自分の音が埋もれて何を弾いているか分からなくなってしまう…こんな経験ありませんか?
そして同じベース、同じアンプ、同じセッティングでも、鳴る人と鳴らない人がいます。
その原因の多くは、実は“右手”にあります。
今回は、ベースの右手テクニックにフォーカスし「しっかり鳴る=芯のある音」を出すための奏法のコツを解説していきます。
STEP:2 【1. 音の芯とは何か?】
「芯がある音」とは、輪郭がハッキリしていて、埋もれない音。
これは弦の振動を的確に引き出し、その振動を楽器本体やピックアップにしっかり伝えることで生まれます。
右手で弦に“正しく”エネルギーを与えることが鍵です。
STEP:3 【2. 指弾きの下準備】
まず、大前提として、両手共に爪はなるべく短く切って整えましょう。
ギターより弦が太いベースでは、弦が爪に接触すると耳障りの悪いカリカリ音やノイズの原因になります。(※深爪に注意!)
STEP:4 【3. 指弾きの基本奏法:アポヤンド】
一つの弦を弾いた時、弾き終えた指が低い方の弦に着地する奏法を「アポヤンド」と言います。
ジャズのウォーキングベースやファンク、R&B等での野太いベースサウンドを出すには、このアポヤンド奏法をしっかりと身に付ける必要があります。
弦を撫でたりつまむように弾くのではなく、しっかりと振動するように弾きましょう。
STEP:5 【4. フォーム:コントラバスの場合】
日常生活ではあまり意識しませんが、人間の腕は意外と重くできています。
ベース、特にコントラバスでは指弾きの際にこの重さを利用して音に輪郭を与えることができます。(※アルコ=弓で弾く際も同様の考え方をしますので、頭の片隅に置いておくと後々便利です。)
試しに、腕をまっすぐに伸ばしたまま手を腰の高さまで持ってきて、そのまま脱力して落としてみましょう。
この「腕を落とす」という動作が「重力を利用して弦に腕の重さを乗せる」ことにつながりますので、意識してみてください。
STEP:6 【5. フォーム:エレキベースの場合】
コントラバスでは腕の重さを利用しましたが、エレキベースの場合は「握力」を利用しましょう。
と言っても「とにかく握力を鍛えよう」ということではなく「正しいグリップ(フォーム)で自分の握力を利用しよう」ということです。
握力計で計測する時、斜めに持ったり、握り込めないようなフォームだと正しく計測できません。
エレキベースもそれと同じで「弦を振動させられる指の配置になっているか」に注意する必要があります。
具体的には、基本フォームは「弾く指は弦に対して垂直」です。
この基本フォームを身に付けた上で、指を斜めにして甘い音色を出したり、弦を押し込んで弾くことで荒々しい音を出したりするバリエーションができますので、しっかりと身に付けましょう。
STEP:7 【6. 右手による音質コントロール】
右手で音質のコントロールをかけられるようになると、不要な倍音が減り、芯のある音が際立ちます。
指板寄りで弾くと暖かみのある音、ブリッジ寄りで弾くとパキッとした立ち上がりの良い音になりますが、どちらで弾くにしても「指の侵入角度・接弦面積」で音の立ち上がりが決まりますので、それぞれの場面に合った音選びができるようにバリエーションを持たせる練習をしておきましょう。
STEP:8 【7. 練習法の一例】
・開放弦のみを使って「芯のある音」を出す練習をしてみよう
・指板側の左手を使わず、右手のフォームと力加減の変化による音の変化に集中する
・録音して、弾いているときと聴いたときのギャップを確認する
STEP:9 【まとめ】
右手テクニックを見直すだけで、ベースの音は劇的に変わります。
芯のある“鳴る”音を出すには、単なる力強さではなく、効率的な動作と身体の使い方が重要です。
ぜひ、今日から右手を見直して、理想のベースサウンドに一歩近づいてみてください。
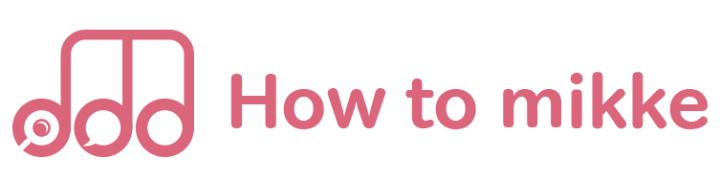
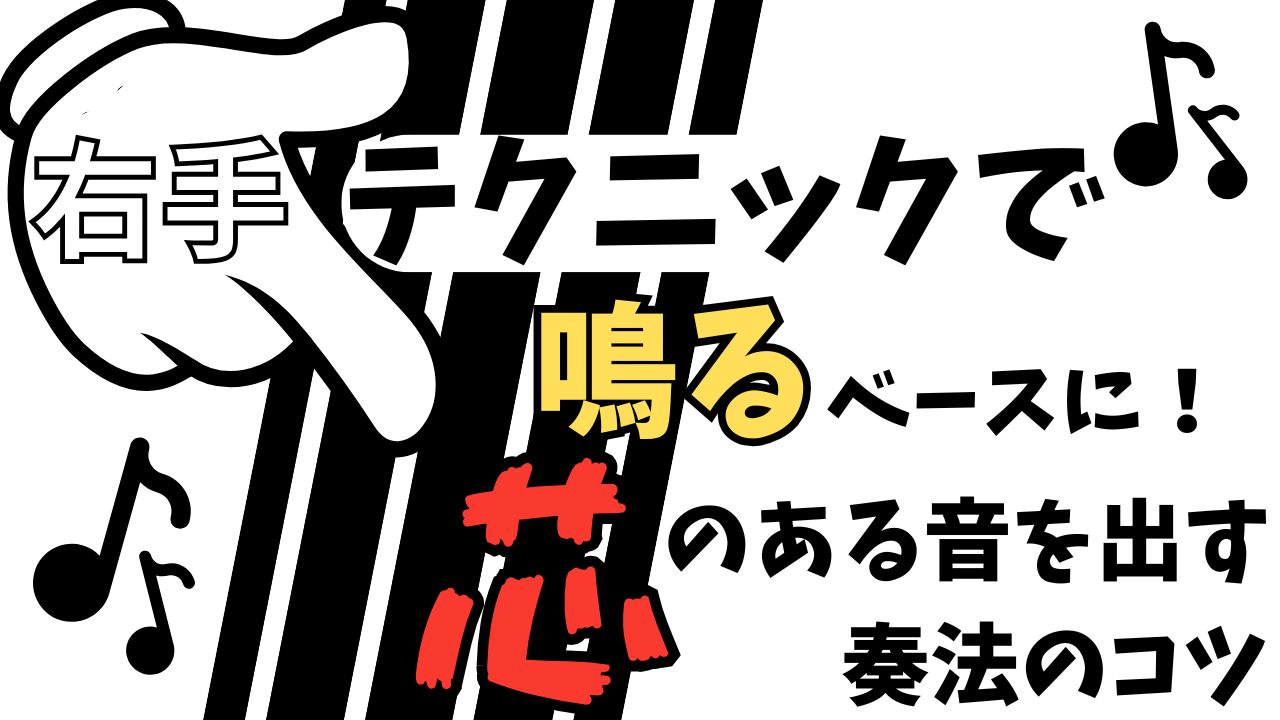

コメント0件