加えて、Ray BrownやPaul Chambersといった名ベーシストの実例を紹介し、理論だけでなく実践的なイメージも掴める構成に。
初心者〜中級者のベーシストに向けて、説得力あるラインを作るための視点と練習のヒントが詰まった内容です。
目次
STEP:1 【はじめに】
ウォーキングベースは、ジャズやブルースの演奏において、曲の土台を支える非常に重要な要素です。
ベースラインを弾く中でコード感をしっかりと伝えるラインを作れるかどうかによって、演奏の説得力や全体のノリが大きく変わってきます。
今回は、ウォーキングベースにおける「コード感」を明確にするための4つのポイントを紹介します。
STEP:2 【1. ルート音を確実に押さえる】
まず最優先なのは、コードのルート音(根音)をしっかりと押さえることです。
コードの頭(各小節の1拍目など)でルートを鳴らすことで、コード進行の基礎がリスナーにもプレイヤーにも伝わりやすくなります。
セッションやバンドアンサンブルでは、これが「コードの基本を提示する」という意味で重要な役割を持ちます。
STEP:3 【2. ガイドトーン(3度・7度)を意識する】
ルートだけではコードの種類(メジャー/マイナー/ドミナントなど)が明確になりません。
3度や7度といった「ガイドトーン」をウォーキングの中に散りばめることで、コード感が格段に強くなります。
例えば、Cm7においてE♭(短三度=マイナーな響き)を使用したり、F7においてA(長三度)を用いることで、コード進行を明快に感じさせます。
また、7度の音を加えることで、コードの響きが複雑になり、より深みのある響きを生み出すことができます。
特に「V7」(あるスケール内の5番目の音から始まるコード 例:Cメジャースケール(C,D,E,F,G,A,B)におけるG7)は、トニックコード(I=Cmaj7)に向かう強い解決感を持ち、音楽の流れを作る上で重要な役割を果たします。
STEP:4 【3. パッシングノートとクロマチックアプローチ】
ベースラインのスムーズな流れとコード感の補強には、パッシングノート(経過音)やクロマチックアプローチ(半音進行)が非常に効果的です。
これは、次に行きたい音との「物理的な距離」を半音・全音で埋めることで、ラインが滑らかになる上に、多くのジャズプレイヤーが用いているので「ジャズらしい」響きになります。
例に用いている「Autumn Leaves(枯葉)」では、Cm7→F7へのコード進行で「E♭→E→F」を用いることでコード間の流れをスムーズな響きにしています。
ただし、入れすぎるとコード感がなくなってしまいますので、適度に使用するよう注意しましょう。
STEP:5 【4. リズムと音価でニュアンスを出す】
全てを均等に弾くだけでなく、わずかな音の長短、アクセント、レイテンシー(後ノリ)を使うことで、コード進行の「うねり」や「躍動感」が生まれます。
これは聴き分けがちょっと難しく、最初は「4ビートって、全部同じに聴こえる…」と思うかも知れません。
コツは、一つの音源・1人のベーシストを聴き込むだけではなく、色んな音源を聴き比べて「このベーシストは前ノリだな」「ここのベースラインは少しタメをきかせてるな」と、知識が増えれば増えるほど「聴き方のバリエーション」が広がっていきますので、焦らずじっくりと聴き込んでみましょう。
【例】
◆ Ray Brown Trio – “Exactly Like You”
アルバム:Live at the Loa (1988)
◆ Paul Chambers – “Yesterdays”
アルバム:Bass on Top (1957)
◆ Ron Carter – “Autumn Leaves”
アルバム:With Jim Hall (1972)
◆ Sam Jones – “Unit 7”
アルバム:Cannonball Adderley Quintet in San Francisco (1959)
STEP:6 【補足:名ベーシストのウォーキング例】
● Ray Brown(レイ・ブラウン)
オスカー・ピーターソン・トリオなどで活躍した超王道ベーシスト。
ルート中心ながらもガイドトーンとクロマチックを絶妙に織り交ぜ、抜群のスウィング感と安定感を生み出します。
「C Jam Blues」などで、シンプルながら芯のあるウォーキングが聴けます。
※Ray Brownは実際の演奏では1拍目をやや前に置くなど、場面によってノリを使い分けています。その結果として、抜群の推進力と安心感を両立させている点に注目してみてください。
▶ ポイント
ルート → 5度 → ガイドトーン → パッシング、という教科書的な構成で、一拍目に絶対的な安心感がある。
● Paul Chambers(ポール・チェンバース)
マイルス・デイヴィス・クインテットで活躍。より動きのあるラインとリズムバリエーションが特徴です。
「So What」「All of You」などで、コードの色彩を活かしたベースラインが聴けます。
▶ ポイント
音価の変化やスライドでニュアンスを出しつつ、コードトーンとクロマチックの使い方がスケールアウトしすぎない絶妙なバランスでベースラインを組み立てています。
STEP:7 【まとめ】
ウォーキングベースは単なる「音符の羅列」ではなく、コード進行の流れをベースラインでどう表現するかが鍵になります。
今回紹介した4つのポイント「ルート、ガイドトーン、パッシングノート、リズム」を意識して練習すれば、コード感のある説得力のあるラインが作れるようになります。
ぜひ日々の練習や実践の中で、意識して取り入れてみてください。
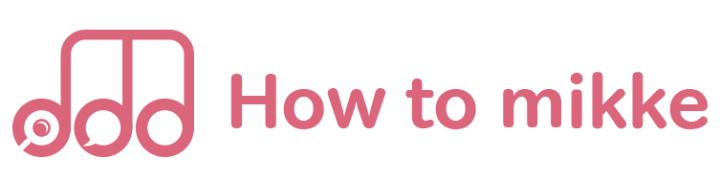
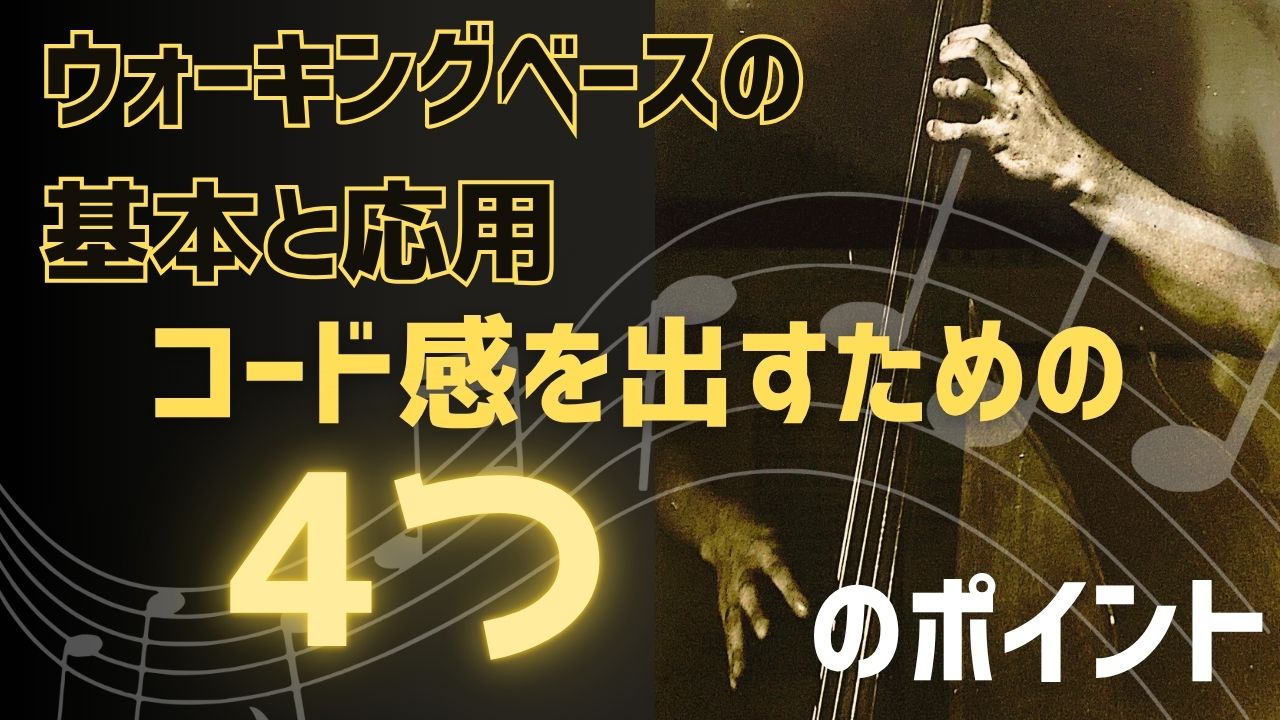

コメント0件